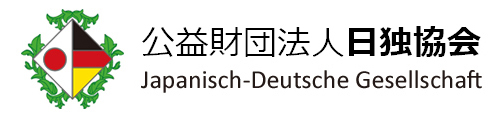懇談会サロンでは、その時々の日独のトピックス、世間の話題、問題等をテーマにします。協会への提案、アドバイスもお話いただける談論風発の会を考えております。
テーマ:ドイツで取得した博士号(Promotion)と教授資格(Habilitation)
懇談要旨:
大変貴重な経験をお持ちの江村牧人先生にドイツ・ハノーバー医科大学における学位(博士号)取得(Promotion)と教授資格取得(Habiitation)についてお話を頂きます。取得についてはそれぞれの地方やさまざまな大学の間に違いがあり、異なる専門分野の間にも違いがあるようですが、共通している部分も数多くあるようです。ハノーバーの場合はミュンヘン大学の規約をしばしば参考にしているようです。
Promotionの口頭試問でのご経験とのことですが、ある物質の化学構造を問われて、予期していなかった質問で、うろたえ、構造の一部分を思い出せず、総合点が合格したものの良くなく、指導教官に苦情を言われた苦い経験があったとのことです。この辺のお話をもう少し詳しくして頂けると思います。 又、Habilitationは1983年で、テーマが “動物とヒトの気管支上皮のステム・セルの培養とその環境汚染物質検索への応用” でした。本来Habilitationでは口頭試問はないはずですが、私はHabilitationの規約をきちんと読んでいなかったので、口頭試問(ディベート)に出席しろという勧告があり、出席したそうです。ディベートでは、動物で得たデータをヒトにいかにして当てはめるか、試験管内で得たデータを自然環境にいるヒトの安全性の予測にどういう風に利用するか、などが真剣に議論されたようです。この話の中で、両方の称号取得のための手続きの流れやPromotion/Habilittionの人数についてもご報告頂きます。
講師:江村牧人氏(経歴は下記に記載)
日時:2024年5月20日(月)18:00~19:30 申込期限:5月17日(金)
会費:無料
定員:25名
場所:日独協会会議室
世話人: 佐藤勝彦理事
申込み:お名前、(公財)日独協会の会員番号、メールアドレス、電話番号を記入の上、世話人の佐藤理事までメールでお申込みください。
世話人連絡先: s-kmtaym(a)nifty.com ※ (a)は@に書き換えて下さい
1964 北海道大学理学部生物学科卒業 1966 北海道大学理学部修士課程動物学専攻卒業
1966 愛知県立がんセンター 生物学部研究員
1976 愛知県立がんせんター 生物学部主任研究員
1973 – 1975 アレグザンダー・フォン・フンボルト財団奨学生 ハノーバー医科大学実験病理学部招聘研究員
1976 ハノーバー医科大学実験病理学部 研究員
1977 ハノーバー工科大学 博士号(Dr. rer.nat.)取得
テーマ:発癌メカニズム解明の鍵として発生途上中にハムスター胎仔気管上皮が示す分化に依存した変化
1981 連邦青年・家庭・保健大臣賞を、“肺由来細胞及び器官培養を用いた芳香族化合物の発癌性の検索“で受賞
1983 Habilitation-venia legendi (Privatdozent) を専門分野‐実験癌学で取得, ハノーバー医科大学教授団のメンバーになる
1983 同時に博士号(Dr. rer.biol.hum.habil.) を取得
1987 員外教授(Apl. Professor)に任命される
1989 終身大学教授に任命される
1990 東京国立がんセンター病理部と共同研究
1995 国立がんセンター柏分院病理部と共同研究
2002 ハノーバー医科大学を定年退官
2004 – 2015 ヴェンチャー企業・Cultex Laboratories顧問
1966 – 2004 日本癌学会、組織培養学会(U.S.A.)、ドイツ癌学会・実験癌学、ヨーロッパ組織培養学会 会員
懇談要旨:
大変貴重な経験をお持ちの江村牧人先生にドイツ・ハノーバー医科大学における学位(博士号)取得(Promotion)と教授資格取得(Habiitation)についてお話を頂きます。取得についてはそれぞれの地方やさまざまな大学の間に違いがあり、異なる専門分野の間にも違いがあるようですが、共通している部分も数多くあるようです。ハノーバーの場合はミュンヘン大学の規約をしばしば参考にしているようです。
Promotionの口頭試問でのご経験とのことですが、ある物質の化学構造を問われて、予期していなかった質問で、うろたえ、構造の一部分を思い出せず、総合点が合格したものの良くなく、指導教官に苦情を言われた苦い経験があったとのことです。この辺のお話をもう少し詳しくして頂けると思います。 又、Habilitationは1983年で、テーマが “動物とヒトの気管支上皮のステム・セルの培養とその環境汚染物質検索への応用” でした。本来Habilitationでは口頭試問はないはずですが、私はHabilitationの規約をきちんと読んでいなかったので、口頭試問(ディベート)に出席しろという勧告があり、出席したそうです。ディベートでは、動物で得たデータをヒトにいかにして当てはめるか、試験管内で得たデータを自然環境にいるヒトの安全性の予測にどういう風に利用するか、などが真剣に議論されたようです。この話の中で、両方の称号取得のための手続きの流れやPromotion/Habilittionの人数についてもご報告頂きます。
講師:江村牧人氏(経歴は下記に記載)
日時:2024年5月20日(月)18:00~19:30 申込期限:5月17日(金)
会費:無料
定員:25名
場所:日独協会会議室
世話人: 佐藤勝彦理事
申込み:お名前、(公財)日独協会の会員番号、メールアドレス、電話番号を記入の上、世話人の佐藤理事までメールでお申込みください。
世話人連絡先: s-kmtaym(a)nifty.com ※ (a)は@に書き換えて下さい
1964 北海道大学理学部生物学科卒業 1966 北海道大学理学部修士課程動物学専攻卒業
1966 愛知県立がんセンター 生物学部研究員
1976 愛知県立がんせんター 生物学部主任研究員
1973 – 1975 アレグザンダー・フォン・フンボルト財団奨学生 ハノーバー医科大学実験病理学部招聘研究員
1976 ハノーバー医科大学実験病理学部 研究員
1977 ハノーバー工科大学 博士号(Dr. rer.nat.)取得
テーマ:発癌メカニズム解明の鍵として発生途上中にハムスター胎仔気管上皮が示す分化に依存した変化
1981 連邦青年・家庭・保健大臣賞を、“肺由来細胞及び器官培養を用いた芳香族化合物の発癌性の検索“で受賞
1983 Habilitation-venia legendi (Privatdozent) を専門分野‐実験癌学で取得, ハノーバー医科大学教授団のメンバーになる
1983 同時に博士号(Dr. rer.biol.hum.habil.) を取得
1987 員外教授(Apl. Professor)に任命される
1989 終身大学教授に任命される
1990 東京国立がんセンター病理部と共同研究
1995 国立がんセンター柏分院病理部と共同研究
2002 ハノーバー医科大学を定年退官
2004 – 2015 ヴェンチャー企業・Cultex Laboratories顧問
1966 – 2004 日本癌学会、組織培養学会(U.S.A.)、ドイツ癌学会・実験癌学、ヨーロッパ組織培養学会 会員
終了した懇談会サロン
2024年
| 2024年4月15日 | ドイツの産業を支える研究・人材政策 | 永野博氏 |
| 2024年3月18日 | 聖書考古学とパレスティナ/イスラエル | 山野貴彦先生 |
| 2024年2月26日 | 日本と西洋の芸術に表現された<死後の世界> ー鎌倉時代の仏教説話画とドイツ中世の版画の比較を中心に | 青山愛香先生 |
| 2024年1月15日 | 私の経験した連邦首相―シュミットからショルツまで | 八木毅 大使 |
2023年
| 2023年12月8日 | シーボルト研究の現在 ーシーボルト来日200周年をむかえて |
堅田智子先生 |
| 2023年11月27日 | ミノックスカメラの歴史・技術とその魅力 | 前川 泰久氏 |
| 2023年10月29日 | これからの日独交流を語る | 相澤啓一 先生 |
| 2023年9月11日 | ”O alte Burschenherrlichkeit"「我が懐かしき青春の日々」~ドイツ語文化圏に存在するStudentenverbindung(学生組合)~ | 植松 健氏 |
| 2023年7月24日 | エストニア大学紀行―タルトゥ大学のドイツ人医師と化学者たち― | 赤羽 良一 先生 |
| 2023年6月26日 | 生涯学習としてのドイツ語 | 中山 純先生 |
| 2023年5月22日 | 明治期の洋行者の欧州文化体験 | ハルトムート・オ・ロータモンド教授 |
| 2023年4月17日 | 本の大学におけるドイツ語教育の今 | 前田 俊秀氏 |
| 2023年3月20日 | メルヒェン初 世界記憶遺産になった『グリム童話』とは? | 虎頭 惠美子氏 |
| 2023年2月28日 | 欧州最大のデュッセルドルフ日本人学校に勤務して | 木田宏海氏 |
| 2023年1月23日 | 西独の誕生:アデナウアーという人 | 黒川剛大使 |
2022年
| 2022年12月17日 | 第一次大戦後、千葉県にあったドイツ兵捕虜収容所 | 金谷誠一郎氏 |
| 2022年11月2日 | 画家アルブレヒト・デューラー | 真野宏子氏 |
| 2022年10月16日 | ライプツィヒの学生生活:現地からの報告 | 大野亘児氏 |
| 2022年9月12日 | 今こそこれからの日独交流を語ろう | 相澤啓一氏、マイト・ピア智子氏、木戸裕氏 |
| 2022年7月27日 | 1960年前後のドイツの状況とアルト歌手ゲルトルーデ・ピッツインガーの人と音楽について | 伊藤光昌氏 |
| 2022年6月21日 | ハンナアーレントと難民問題 | 矢野久美子氏 |
| 2022年5月30日 | ドイツの大学:昔と今 | 木戸裕氏 |
| 2022年4月18日 | 地球温暖化-20年間計測してみてわかったこと | 石川宏氏 |
| 2022年3月24日 | 西独しか知らない男が見た今日のドイツ | 黒川剛氏 |
2020年
| 2020年2月21日 | 知ってるようで知らない砂糖の話 | 金谷誠一郎理事 |
| 2020年1月26日 | 森鴎外とドイツ語の名前 | 美留町義雄氏 |
2019年
| 2019年11月18日 | ハーフのグラフィックデザイナーとして | リサ・アイト氏 |
| 2019年10月21日 | 言語習慣による声楽家の発声テクニックの違いについて | 藤田 明氏 |
| 2019年9月30日 | 歯の健康と「歯の咬み合わせ」について | 加藤和子氏 |
| 2019年6月24日 | 反ユダヤ主義の歴史と現状 | 村山雅人氏 |
| 2019年4月26日 | 「西方見聞録」西ドイツ一周研究旅行全記録1964年2月24日~10月9日 | 瀧澤敬三氏 |
| 2019年3月25日 | 「上皇」の歴史―承久の乱の中世と生前退位の現代―ドイツ滞在の経験から | 坂井孝一氏 |
| 2019年2月25日 | ケルン日本文化会館と日独文化関係 ~ドイツ滞在の経験から~ | 坂戸勝氏 |
| 2019年1月28日 | 美智子皇后陛下歌集『その一粒に重みのありて』講読会 | 村上綾氏 |
2018年
| 2018年11月19日 | ドレスデン、ザクセンの歴史と産業 | 伊崎捷治氏 |
| 2018年10月15日 | ドイツ・デュッセルドルフの恵光寺の建築物語とその当時の背景 | 柄戸正氏 |
| 2018年9月21日 | 北朝鮮の庶民生活の実体 | 北岡裕氏 |
| 2018年7月23日 | 近代を振り返る:欧米のしたことは欧米のしたこと そして日本のしたこと | 仲津真治氏 |
| 2018年6月25日 | 還暦を控えて声楽を始め、10年間に3回の手作りオペラ・リサイタル(歌と講演)を成功させるまで | 坂東道代氏 |
| 2018年4月27日 | 第一次大戦前夜のウィ―ンで活躍した2人の芸術家 | 村山雅人氏 |
| 2018年3月19日 | ドイツの鉄道博物館を巡って | 久保健氏 |
| 2018年1月15日 | 大学改革の今―ドイツの大学・日本の大学― | 木戸裕氏 |
2017年
| 2017年11月10日 | ベルリン封鎖と朝鮮戦争 | 本多巍耀氏 |
| 2017年10月16日 | 有田焼とマイセンの関係 | 蒲原 裕氏 |
| 2017年9月25日 | シルクロードの都市遺跡と、ユーラシアが生み出してきたパワー | 仲津真治氏 |
| 2017年7月14日 | 今後のEU | 黒川剛氏 |
| 2017年6月5日 | ケンペルとオランダ通詞今村源右衛門英生 | 今村公子氏 今村昌明氏 |
| 2017年4月24日 | 第一生命の保険はドイツから | 金泉秀樹氏 |
| 2017年3月17日 | レーザー光線はすごい! | 渡部武弘氏 |
| 2017年2月20日 | 私の翻訳書 | 岡田朝雄氏 |
| 2017年1月16日 | 二期会の歴史とドイツオペラの関係 | 中山欽吾氏 |
2016年
| 2016年11月18日 | 古代ギリシアの歴史と文明を訪ねて 東地中海クルーズの旅 | 仲津真治氏 |
| 2016年10月17日 | ソ連の核実験とドイツ人スパイ | 本多巍耀氏 |
| 2016年9月16日 | ベートーベンはドイツ人? | 藤田俊之氏 |
| 2016年7月15日 | Gerhard Hueschの最期に想う | 麻生英臣氏 |
| 2016年6月20日 | 世紀末ウィーンとユダヤ人 | 村山雅人氏 |
| 2016年5月23日 | 150年にわたり日本・ドイツ・アメリカの狭間に生きたヘルム一族の中で日独交流 | レスリー・ヘルム氏 |
| 2016年4月18日 | バイロイト音楽祭の想い出 | 小山元氏 |
| 2016年3月4日 | 旅することは生きること”ザクセン州蒸気機関車の追いかけ旅 | 田中貞夫氏 |
2015年
| 2015年11月9日 | 分断のドイツから統一のドイツへ DDRでのビジネスマンとしての体験も | 市村光世寧氏 |
| 2015年10月9日 | 日本とドイツの文化財・歴史的建造物 | 近藤貴子氏 |
| 2015年9月14日 | ドイツ好きが語るドイツあれこれ | 高橋忠夫氏 |
| 2015年7月13日 | 久々のアメリカ、建国の原点に立ち返って。 | 仲津真治氏 |
| 2015年6月22日 | 2014年ドイツの社会・経済情勢 | 伊崎捷治氏 |
| 2015年6月01日 | 「椿の絆」 | 柄戸正氏 |
| 2015年4月27日 | マックス・ウェーバーと現代資本主義 | 堀田博司氏 |
| 2015年3月16日 | 「ベルリンの壁」建設と崩壊を現場で見た | 織田正雄氏 岩本晢氏 |
| 2015年2月23日 | 「ヘルマン・ヘッセと昆虫」-文豪が生涯愛し続けた蝶たち- | 岡田朝雄氏 |
| 2015年1月19日 | 新入会員懇談会 |
2014年
| 2014年11月14日 | 「対馬」 フランク・ティース著 柄戸 正訳(文芸社刊) | 柄戸正氏 |
| 2014年10月20日 | 「ドイツ民謡」と「日本の唱歌」 | 横山淳子氏 |
| 2014年9月22日 |
「日独美術に見る終末ヴィジョン」 ~デューラー『黙示録』(1498年)と 13世紀鎌倉絵巻『聖衆来迎図の六道絵』の比較 |
青山愛香氏 |
| 2014年7月18日 |
「日本企業のグローバル化と人材育成 ―ドイツでの日本企業の活動を中心に-」 |
柚岡一郎氏 |
| 2014年6月23日 | 「数字で比較する日本とドイツ」 | 伊崎捷治氏 |
| 2014年5月19日 | 「ドイツ(欧州)駐在中のあれこれ」 | 出原悠氏/当協会理事 |
| 2014年4月18日 | ドイツ(が好きな日本)から見たサッカーワールドカップ | 小西敏夫氏 |
| 2014年3月10日 | ナチスはどの程度「ドイツ的現象」か | 黒川剛 大使 |
| 2014年2月17日 | 健康・長寿をスマートに | 大竹登志子 氏 |
2013年
| 2013年11月18日 | 私の見た戦後ドイツの宰相たち | 黒川剛 大使 |
| 2013年10月21日 | 南米へのドイツ移民 | 宇治孝 氏 |
| 2013年7月12日 | JTBフランクフルト支店に5年半駐在して | 井上 敏子 氏 |
| 2013年6月24日 | バイエルンの山歩きを楽しむ その2 | 吉田薫 氏 |
| 2013年5月13日 | ベルリンの桜めぐり |
菅家力 氏 |
| 2013年4月15日 | ヤルタ会談とドイツ分割 |
本多巍耀 氏 |
| 2013年3月4日 | 日本の大学法学部にドイツ法が設けられている理由 | H. Menkhaus 氏 |
| 2013年2月18日 | デュッセルドルフ日本人学校について | 岡田裕 氏 |
| 2013年1月11日 | インド紀行 | 仲津真治 氏 |
2012年
| 2012年11月19日 | バイエルンの山歩きを楽しむ | 吉田薫 氏 |
| 2012年10月1日 | ①「終戦直後のドイツ その2-戦争裁判」 ② 戦時下のウィーン脱出-故村田豊文氏の記録から |
①岩本晢 氏 ②廣田貞子 氏 |
| 2012年9月14日 | 日独協会懇談サロン「終戦直後のドイツ」 | 田口義孝 氏 |
| 2012年7月23日 | 日独協会懇談サロン「ドイツ国家のしくみ」 | Felix R. Einsel 氏 |
| 2012年6月01日 | 日独協会懇談サロン | 岩本晢 氏 |
| 2012年2月20日 | 日独協会懇談サロン | 出原悠 理事 |
2011年
| 2011年11月14日 | 南ドイツロマンティク街道旅 | 田中貞夫 氏 |
2010年
| 2010年8月23日 | ドイツサッカー 強さの秘密 | 明石真和 氏 |
| 2010年7月12日 | 軽井沢でドイツ三昧 |
越中屋学 氏 對馬良一 氏 |
| 2010年6月25日 | イースターって何ですか? | 雨宮慧 氏 |
| 2010年5月17日 | Münchner Allerlei! ミュンヒェンざっくばらん ~南ドイツ通信(補遺)~ |
光野正幸 氏 |
| 2010年4月19日 | バッハ、シューマン、それともポルシェ? …ライプツィヒは今年も熱い! |
坂田史男 氏 |
| 2010年3月15日 | 新 入会員顔合わせ会 | |
| 2010年2月8日 | 私の旅行スタイル「音楽と世界遺産に誘われて」 | 菅家力 氏 |
| 2010年1月4日 | 賀詞交換会(当日の様子は事務局ブログをご覧ください) |
2009年
| 2009年11月9日 | 神聖ローマ帝国の宝冠 | 渡辺鴻 氏 |
| 2009年10月19日 | 第二次世界大戦 -開戦の引き金ー | 岩本晢 氏 |
| 2009年9月14日 | ドイツ発見の旅 -フランケン地方- | 小野岩雄 氏 |
| 2009年7月13日 | 梅酒プローベ | Nicolas Soergel 氏 |
| 2009年6月8日 | 歴史に埋もれたドイツのカミカゼたち | 三浦耕喜 氏 |
| 2009年5月11日 | 木の温もりに魅せられて―ドイツ木製工芸の話 | 中村一行 氏 |
| 2009年4月13日 | 国境を越えた労働者の稼動 | 森廣正 氏 |
| 2009年3月9日 | 新入会員顔合わせ会 | |
| 2009年2月9日 | DIE WELT DER 60± MÄNNER | Paul
Kuhn 氏 Paul Hermes 氏 |
2008年
| 2008年11月10日 | 田島直人を語る |
| 2008年10月6日 | ドイツレストラン『シュタインハウス』開店談 |
| 2008年8月25日 | オーバーアマガウ キリスト受難劇 |
| 2008年7月14日 | ドイツ人と日本人の旅行とは? 旅行会社に見る日独比較 |
| 2008年6月9日 | ブリキおよび珪素鋼ハンの国産化を成功させたヴァルター・ルオフスキ |
| 2008年5月12日 | モーツァルト:親子3代の音楽と楽才は?-レオポルドへのオマージュ- |
| 2008年4月8日 | 京阪神でドイツ語教育に一生を捧げた ユーバーシャール先生との思い出 |
| 2008年3月10日 | ドレミの発祥 ーいまさら聞けない音楽理論入門 |
| 2008年2月4日 | 日本の教育の礎になったドイツ人カルシュ |
| 2008年1月7日 | 賀詞交歓会 |
2007年
| 2007年11月12日 | 日系企業の対独(欧)進出の現状 |
| 2007年10月15日 | ドイツ 冬の歳時記 |
| 2007年9月10日 | ビール話は止められない |
| 2007年7月9日 | ドイツの開発プロジェクト 歴史的拠点探訪 |
| 2007年6月22日 | 日本とドイツのお肉の話(JGとの合同企画) |
| 2007年5月14日 | 今年も日本で歌声を披露するマックス・ラーベ―その魅力に迫る― |
| 2007年4月9日 | 教科書会議の歴史と成果 |
| 2007年3月12日 | タウヌス 森と人間 |
| 2007年2月19日 | 童話づくりの裏話 |
| 2007年1月5日 | 賀詞交歓会 |